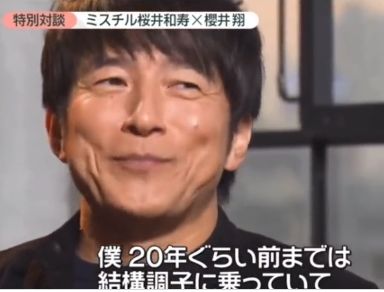片山さんはコストカッター。特に生活保護バッシングで有名だ。 維新と組んで、生活保護の医療扶助無料をやめてほしい。 【特集・生活保護を問う】芸人母受給追及「悪い流れ止める抑止力に」 進む改革・片山さつき氏インタビュー

芸人母受給追及「悪い流れ止める抑止力に」 進む改革・片山さつき氏インタビュー

生活保護費の大幅カットを掲げる自民党の政権復帰で、制度改革の動きが一気に加速している。給付水準の引き下げに加えて、法改正の動きも本格化。不正受給対策として自治体の調査権限を拡充するほか、罰則強化の方向で調整が進む。「働く方が損になる」という国民の不公平感を解消し、本来の意味での「最後のセーフティーネット」に立ち返らせることができるのか。芸能人の母親の受給問題を機に、見直し議論の旗振り役となった同党の片山さつき参院議員に今後の方向性を聞いた。
なんの義務もない「もらう側」
--厚生労働省が生活費に充てる「生活扶助」の基準額を引き下げる方針を固めた
「いよいよ水準が適正化、公平化されるという思いだ。初めて生活保護制度に疑問を感じたのは、大蔵省主計局の厚労省担当主査だった平成7年ごろ。失業手当などさまざまな厚労関係の手当を見ていて『生活保護制度って、もらう側にほとんど何の義務もないな』とはたと気づいた。ハローワークへの登録義務もないんだな、と。海外では職業訓練やコミュニティーサービスなど、何らかの義務がある」
「当時の生活保護費は1兆円台。申請段階での厳正な審査と恥の文化がまだ残っていたことで抑制されていたが、それがなくなったときに『どうやって止めるの?』と当時から思っていた。実際にそういう状況になっている」
--昨年、人気お笑い芸人の母親が生活保護を受給していたことが発覚。片山議員をはじめ何人もが国会で取り上げ、「十分な収入があるのに、扶養義務を果たしていない」との世論が高まった。改めてこの問題を振り返り、どう感じるか
「十分な余裕があって親を養いうる人が、親を積極的に生活保護状態にし、それを周囲に吹聴していた。そんなことをされると、日本中の福祉事務所が困る。そういった悪い波及効果を止める抑止力になった部分はあると思う」
「誤解しないでほしいのは、この問題が表面化する前から、生活保護があまりにもざるになっていて、正直者がばかをみる制度になっているという観点から国会でも取り上げていた。あの問題がなくても、制度改正は実現していたと思う。ただ、国民に『もらい得は許さない』という認識が深まったのは意義があった。私のところには、5千件もの応援メールが届いた」
--一方で、片山議員らに対して「受給者バッシング」「弱者いじめ」との批判の声も寄せられた
「そうした批判はつきもの。引き締めを図ろうとすれば、既得権を守ろうとする人たちは、激しく抵抗する。行き過ぎた既得権を是正し、公平にするのが政治だ」
「ズルもらい」防止を
--自民党政権で、優先的に取り組む見直しのポイントは
「制度の信頼回復という観点からは、まず罰則や取り締まりの強化。例えば、不正受給に対する罰金を現行の30万円以下から100万円以下に引き上げたり、不正受給分を返還する際には、加算金を追徴したりする。見つかったら大ごとになるという抑止力で『ズルもらい』を防止しないといけない。受給者や扶養義務者に説明を求める権限を明確化したり、調査権の強化や対象拡大も必要だ。そうやって不正を減らすことで、不公平感の是正にもつながる」
--必要な人のみに保護の網をかけられれば、負担する国民の同意も得られる
「働いた方がもらえるお金が少ないとなれば、誰も生活保護から抜け出そうとしない。給付水準を下げ、働いて得た収入は保護費から削るのではなく、貯蓄しておいて保護から抜けたときに渡す。就労支援にも力を入れて、まず働ける世代を求職者支援など別のセーフティーネットで受け止め、自立促進することが非常に大切だ」
「ケースワーカー(CW)の増員も必要。実際にCWを増やした自治体では、人件費の増加分より十分なチェックで節減できた保護費の方が大きい、というところがほとんど。今は、総務大臣政務官という立場になったが、国・地方の人事行政は総務省の所管。福祉事務所の態勢をどうするか考えられるので、非常に生活保護制度を見守りやすい立場になった。家族という単位を大切にし、まずは家族、次は地域で、生活保護を受ける人をつくらないようにしなければならない。日本人が古くから持っていた矜持(きょうじ)に基づくような制度にしたい」
--改革のタイムスケジュールは
「自民党の生活保護に関するプロジェクトチームがまとめた生活保護法の改正案は、すでに厚労省にも伝えてある。厚労省側から今国会にも改正法案を提出してもらいたい