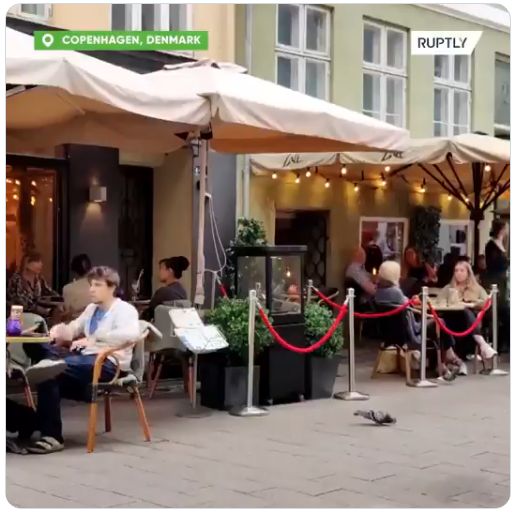タワマン建てすぎで経済が低迷 胡錦涛氏の勢力に移行する可能性 元米総領事

■失脚の可能性が浮上し始めた
足許、海外メディアで、中国の習近平国家主席が健康不安で引退するのではとの報道が出ている。
6月28日には、米国の中国通の一人と目されるグレゴリー・スレイトン氏(元バミューダ米国総領事)が、ニューヨークポストに「習氏の失脚は近いのか」と題した論考を出した。
スレイトン氏は、8月の党中央委員会第4回全体会議(4中全会)で習氏は引退するか、あるいは、名目上の肩書だけを残して、権力を胡錦涛氏らの勢力に移行する可能性が高いと指摘した。
習氏は、7月上旬の“BRICS首脳会議”を、国家主席に就任後初めて欠席した。軍部の人事に関しても、習近平派とみられる人物が主要ポストから離れるケースも確認されている。
習氏失脚説の背景には、中国経済の低迷があるとの指摘は多い。
就業機会を求め内陸部の農村から、北京、上海、深圳などの大都市に出稼ぎに出た人(農民工)や若年層は、厳しい現実に直面することが多い。出稼ぎ目的の多くの人々が、医療や失業保険を受けられず、住宅も買えないという話が聞こえてくる。若者や農民工の多くが、将来に絶望を感じているとの見方もある。
一方、ここへ来て、習政権は経済・社会への統制を一段と引き締めている。
そうした状況では、ヒト、モノ、カネの海外流出は加速し、市民生活の苦しさは高まる可能性がある。しかも、中国では、国の最高意思決定権者を選出する、公平で民主的なルールが見当たらない。
今後、中国国内で権力闘争が激化し、社会、経済、金融市場の不安定感が追加的に増すリスクは高まるとみるべきだろう。
■習近平が生み出した不動産バブル
現在、中国政府の政策は、人々の自由な発想よりも社会、経済の統制をより重視している。
2012年の習政権発足直後、政府は投資を積み増し高い経済成長率を維持しようとした。特に重視したのが、マンションなど不動産投資の積み増しだった。フィンテック分野ではアリババやテンセントが急成長した。
土地が公有(国有)の中国では、人々のマイホームへのあこがれはかなり強い。
習政権発足当初、内陸部ではインフラが未整備の地域も多かった。住宅の需要は膨大だったといえる。それに目をつけた地方政府は、不動産デベロッパーに土地の利用権を売却して歳入を増やしインフラ投資の原資とした。
不動産デベロッパーは需要拡大期待の高い、高層マンションなどの建設を急増させた。住宅市場では、買うから上がる、上がるから買うという強気心理が連鎖し、バブルが膨張した。雇用・所得環境も上向いた。
ただ、資産の価格が永久に上昇し続けることはありえない。
■バブル崩壊のダメージは想定以上
2020年夏場以降、当局の規制によって不動産バブルは崩壊し、その後、住宅価格の下落は鮮明化した。そのあたりから、中国政府は民間企業への締め付けを強めた。
象徴的だったのは、2020年11月にアリババ傘下の金融企業、アント・グループの新規株式公開(IPO)の延期強制だ。
習政権は共同富裕策も打ち出して、民間企業に社会事業への寄付を増やすよう指示した。国防費よりも治安維持などの公安費が上回る年も増えた。人民解放軍や共産党内部では、幹部の更迭や失脚も増えたと聞く。2023年7月には、国家安全保障体制の引き締めに向け“反スパイ法”を改正した。経済統制を優先する政策方針は日増しに鮮明になっている。
バブル崩壊のインパクトは習政権の想定を上回ったのだろう。
バブル崩壊から5年近くが経過したが、住宅価格が下げ止まる兆しは見られない。家計も企業も、今後の資産価格の下落を見越して消費や投資を決める動きが加速し、デフレ圧力は上昇傾向にあると考えられる。
7月3日の人民日報には、経済政策に精通した故李克強前首相の功績をたたえる記事があった。党内でも習政権の経済運営に対する懸念、不満、批判は増えているだろう。
2025年7月10日 7時0分 現代ビジネス
https://news.livedoor.com/article/detail/29135432/