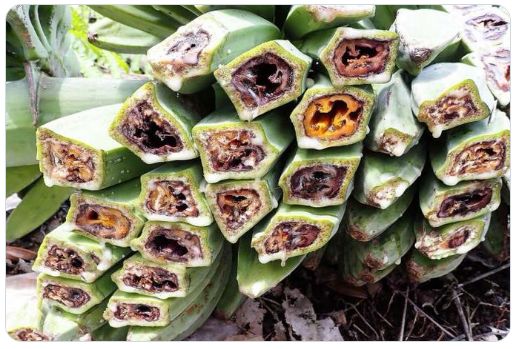志村けん

1970年代初頭、20歳前後の志村けんさんは、大学受験に失敗し定職に就かずフラフラしていた時期に、ザ・ドリフターズのファンとして東京・浅草の劇場に通っていました。そこで、ドリフのメンバーだった荒井注さんに直談判し、弟子入りを志願。荒井さんは志村さんを「付き人」として受け入れ、自宅に居候させながら、舞台の裏方や雑用を任せつつ、芸の基礎を厳しくも愛情深く教え込みました。
荒井さんは志村さんに「芸は真剣に、だが楽しく」をモットーに指導。舞台でのタイミングや観客の笑いの取り方を徹底的に叩き込み、失敗しても「次で取り返せ」と励まし、その才能を信じて育てました。志村さんも荒井さんのユーモアセンスと人間性に心酔し、荒井さんの「間」や「天然」の笑いは、後の志村さんのコメディスタイルに大きな影響を与えました。荒井さんの自宅で生活する中で、荒井さんの家族とも親しくなり、単なる師弟を超えた家族的な絆を築き、荒井さんは志村さんを「息子のように可愛がった」と周囲が証言しています。
弟子入り初期、志村さんが舞台でアドリブを試みて失敗した際、荒井さんは厳しく叱りながらも、「その失敗が大事だ。そこから学べ」と諭しました。この教えは、志村さんが後に「失敗を恐れず挑戦する」スタイルを確立する原点となります。
1974年、荒井さんがドリフターズを引退する際、志村さんは荒井さんの推薦で正式メンバーとしてドリフに加入。荒井さんは「俺の代わりはお前しかいない」と伝え、志村さんに大きな信頼を示しました。志村さんは「荒井さんの穴を埋めるプレッシャーだった」と後に語っています。
志村さんが1980年代に活躍した番組では、荒井さんの「天然ボケ」の影響を受けたキャラクターを生み出し、「荒井さんのあのゆるい笑いが、僕のコメディの原点」と明かしています。2000年に荒井さんが亡くなった際、志村さんは葬儀で「荒井さんのおかげで今の自分がある。僕の芸は荒井さんの延長です」と涙ながらにスピーチ。荒井さんの写真を自宅に飾り、毎年命日には墓参りを欠かさなかったといいます。
荒井さんの「間」や「予測不能なユーモア」は、志村さんの即興性や観客を驚かせるスタイルに直結し、特に「静かなボケ」が志村さんの「動と静のバランス」に反映され、数々のコントで活かされました。売れない時代に荒井さんから生活の支援を受け、芸人としての自信を育まれた志村さん。荒井さんの「笑いは人を幸せにする」という哲学は、志村さんが「子供からお年寄りまで笑えるコメディ」を追求する姿勢へと繋がりました。この深い師弟の絆は、志村けんという稀代のコメディアンを生み出し、彼の人生と芸風に多大な影響を与え続けた感動的な物語です。